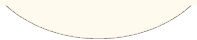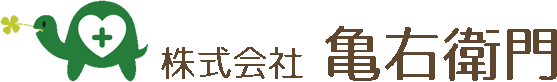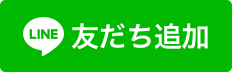社長ノート
Kameemon Leader’s Note 2025年5月号
「介護と金融に共通する“成長の視点”」
金融の世界では、成長とは単なる数字の増加ではなく、価値の持続的な向上を意味する。投資をする際、「短期的な利益を求めるのではなく、長期的な価値を高めること」が重要視される。これは、介護においても同じことが言える。
介護は、単なる「支援」ではなく、「その人の人生の可能性を広げるもの」でなければならない。どのようにすれば、介護を受ける人の“人生の価値”を高めることができるのか——この視点を持つことが、これからの介護の在り方を大きく変えていく。
短期的な支援ではなく、長期的な成長を
金融の世界では、短期の市場の変動に振り回されるのではなく、「長期的にどう成長させるか?」が問われる。介護も同じように、「今この瞬間のケア」だけではなく、「その人が5年後、10年後にどんな生活を送りたいのか?」を考えた支援が求められる。
たとえば、歩行が難しくなった高齢者に対して、すぐに車椅子を提供するのではなく、リハビリを取り入れ、少しでも自分の足で歩けるような環境を作る。これこそが、長期的な成長を考えた介護の姿勢であり、「未来の可能性」を広げる介護の本質だ。
イギリスでは、「エンパワーメント(Empowerment)」という概念が介護において重要視されている。これは、「本人が持つ力を最大限に引き出す」ことを目的とした考え方だ。日本では、「介護=手厚い支援」というイメージが強いが、実際には「支援を最小限にしながら、本人の力を引き出すこと」が、結果的に介護の質を向上させ、長期的な持続可能性を高めることにつながる。
分散投資の考え方と介護の多様性
金融では、「リスク分散」のために、複数の投資先を持つことが推奨される。特定の市場や銘柄に全てを投じるのではなく、バランスよく投資を分けることで、安定した成長を目指す。
介護においても、「一つの方法に依存しない多様な支援」が必要だ。たとえば、日本の介護では「在宅か、施設か」という二択になりがちだが、イギリスでは「エクストラケア・ハウジング」「デイケアセンター」「コミュニティ支援」など、様々な選択肢が用意されている。こうした多様な選択肢を持つことで、一人ひとりに合った最適な支援が可能となり、結果的に介護の持続可能性が高まる。
2025年、介護の未来を広げるために
介護とは、「目の前の課題を解決する仕事」ではなく、「その人の未来をつくる仕事」である。
人は、感動と感激が行動を変える。そして、その行動が、介護の未来を創る原動力となる。
2025年、私たちは「長期的な成長」という視点を持ち、介護の本質を見つめ直す年にしたい。短期的な対処ではなく、長期的に見て介護がより良い形で発展するために、どのような仕組みを作るべきか。金融の視点から介護を考えることで、新しい可能性が見えてくるはずだ。
株式会社亀右衛門 代表取締役社長 福嶋 俊造